タケノコの瓶詰め
梅雨前の里の旬と言えばタケノコ。独特の風味と歯応えは他には代えがたい。出る時は一気に出て、すぐになくなるから、食べ逃すと約1年待つハメになる。そこで役立つのが瓶詰めの「保存食化」だ。今回はヌカを使うよりオススメのダイコンによるアク抜きも紹介しよう。
その日のうちに食べられる
昔の食べ物の旬を調べると現在の5月15日頃に「竹笋生(たけのこしょうず)」とある。ここからタケノコの旬が始まるというワケで、今より約1ヶ月旬が遅い。地球の温暖化がこういうところでもわかる。南の海の魚が北上している話も聞く。本誌読者なら無関心ではいられない問題だろう。
採ってすぐのタケノコは皮付きのまま炭火で焼いて、皮を剥いて食べると実に旨い。タケノコ採りの特権だが、普通の人はなかなか味わえない。売っているものや、もらったものは調理の前の下拵えとしてアク抜きが必要になる。昔から伝わっている方法は米ヌカを混ぜた水で煮て1晩おくというものだが、今回紹介しているのはダイコンの汁を使った方法だ。
ダイコンを使うアク抜きのメリットはいくつもある。1、ヌカよりも入手しやすい。2、ヌカだと手がかゆくなる人もいるが、ダイコンではそれがない。3、アク抜きに1晩寝かせる必要がなく、2~3時間で済むので、その日のうちに料理が食べられる。4、ヌカの匂いが残らず、タケノコ本来の爽やかな香りが楽しめる。
そして、保存食化の重要なポイントである瓶詰めだが、ナポレオンの軍用保存食の方法として採用されてから長い歴史を持つ方法で、シンプルかつ信頼性も高い。きちんと手順を踏めば、水煮でも常温(冷暗所)保管で1年保存可能なので覚えておいて損はない。

使うダイコンの量は皮を剥く前のタケノコの重さの半分というのがわかりやすくていい。当然ながらアク抜き作業は採ってから早ければ早い方がいい。店で買うなら朝イチで買いに行って、家に帰ってすぐ作業をしよう。

タケノコのアク抜きに使うのはダイコンの絞り汁だけだが、残ったダイコンおろしは捨てずに小分けにして凍らせておくといい。後で様々な料理に使うことができる。

切ったタケノコを水から煮る。厚切りにしていないから、沸騰してから5分程度煮るだけで十分。多少煮すぎても、大して歯応えが変わらないのがタケノコのいいところ。

写真・文 鈴木アキラ
1960年生まれ。料理と刃物研ぎが大好きな飲んべえアウトドアライター。「アウトドアで活躍!ナイフ・ナタ・斧の使い方(山と渓谷社刊)」ほか著書多数。












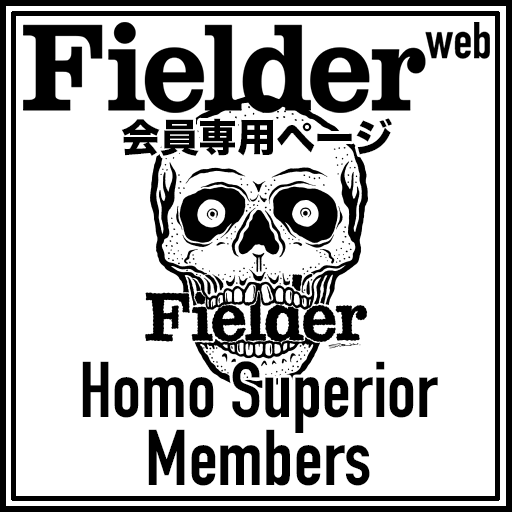















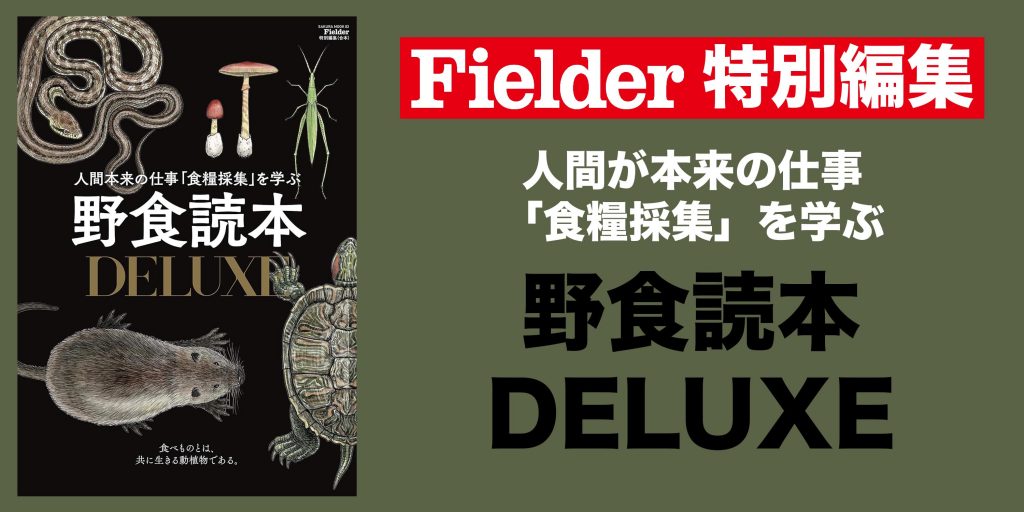
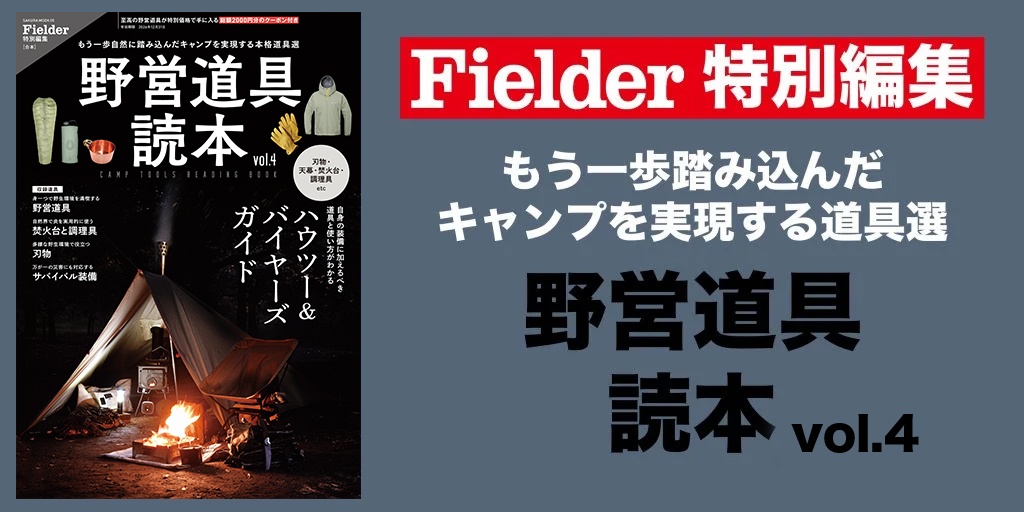
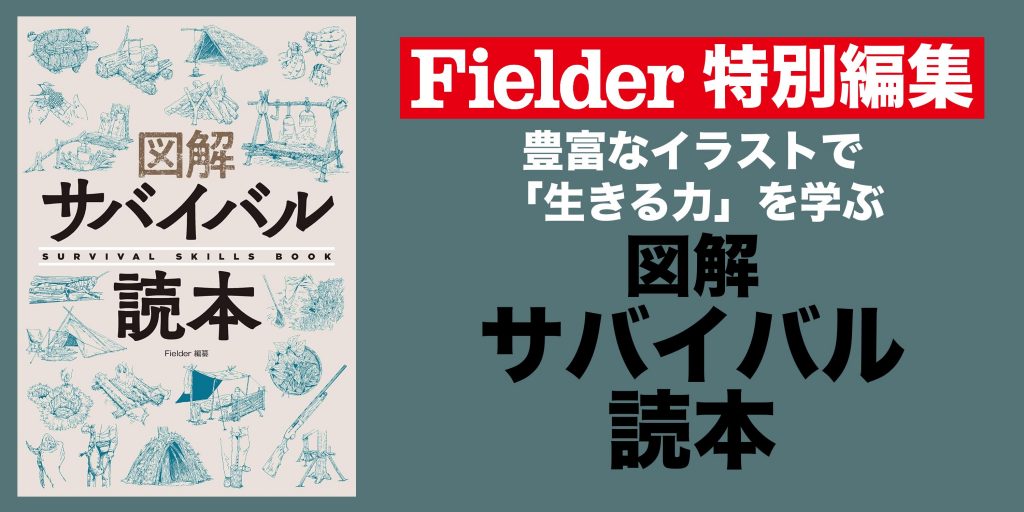
【材料】(Φ8×高さ13cm程度の瓶2本分)
タケノコ:約1600g、ダイコン:約800g、塩:ダイコンの絞り汁と同量の水を合わせた量の約1%の量(今回は約12g)、酢大さじ2
【作り方】
1. ダイコンをキレイに洗ってから皮のまますり下ろす。
2. 水気を絞って絞り汁の量を計る。
3. 絞り汁と同量の水を足す。
4. ダイコンの絞り汁と水を合わせた量の約1%の量の塩を加える。
5. タケノコの皮を剥き、根元の硬い部分は切り落とす。太いものなら4等分、細いものなら縦半分にしてから約1cmの厚さに切る。
6. ④に2~3時間浸ける。
7. 流水で洗い流す。
8. 水から煮立たせて沸騰したら3~5分程度煮る。
9. 再度流水で洗ってアク抜き完了。
10. 煮沸消毒した保存瓶に⑨を詰める。
11. 瓶1個につき大さじ1杯の酢を足してから、瓶の口ひたひたになるまで水を注ぎ、ほんの軽く蓋を閉める。
12. 鍋の中で瓶の肩口まで水につけて40分程度沸騰状態で湯煎する。
13. 一度火を止め、瓶の蓋を取り溢れるまで熱湯を注ぎ、逆さにして空気が入っていないことを確認してから、今度はしっかり蓋を閉める。
14. さらに湯煎すること30分。
15. 鍋から瓶を取り出してゆっくり冷ます。
16. 冷暗所なら常温で1年程度保存が可能。