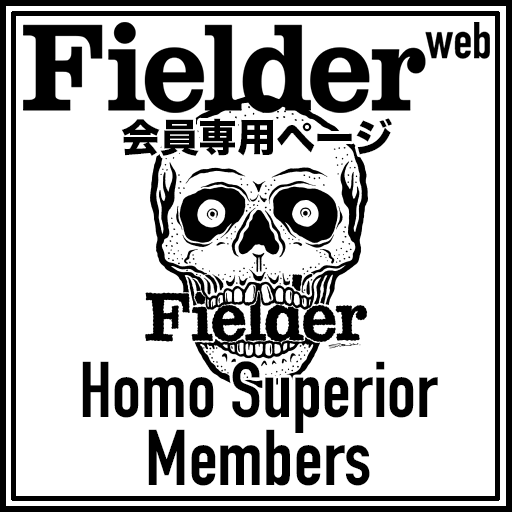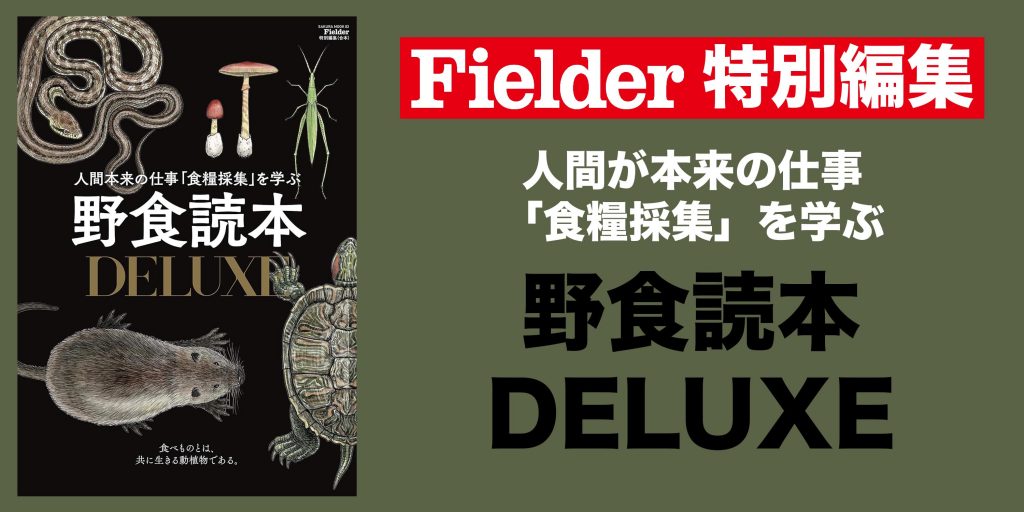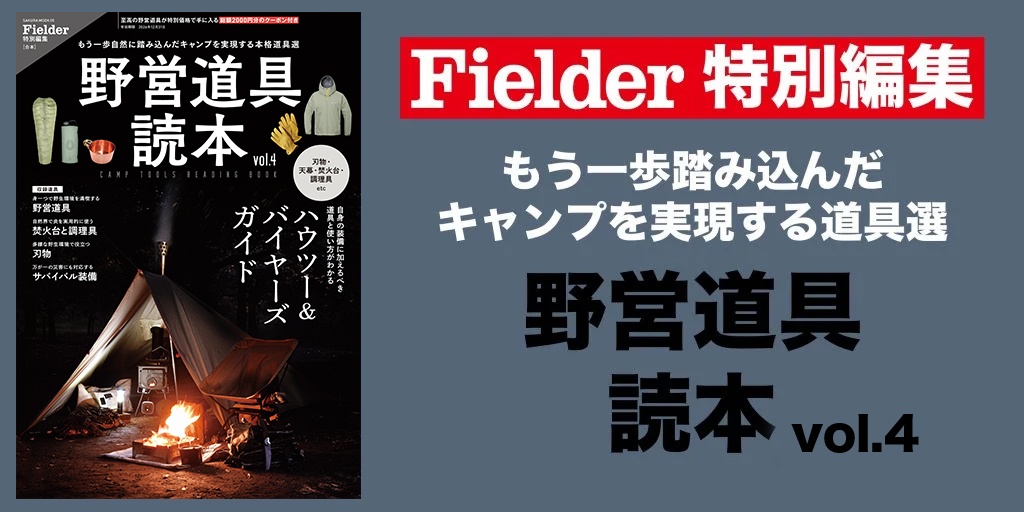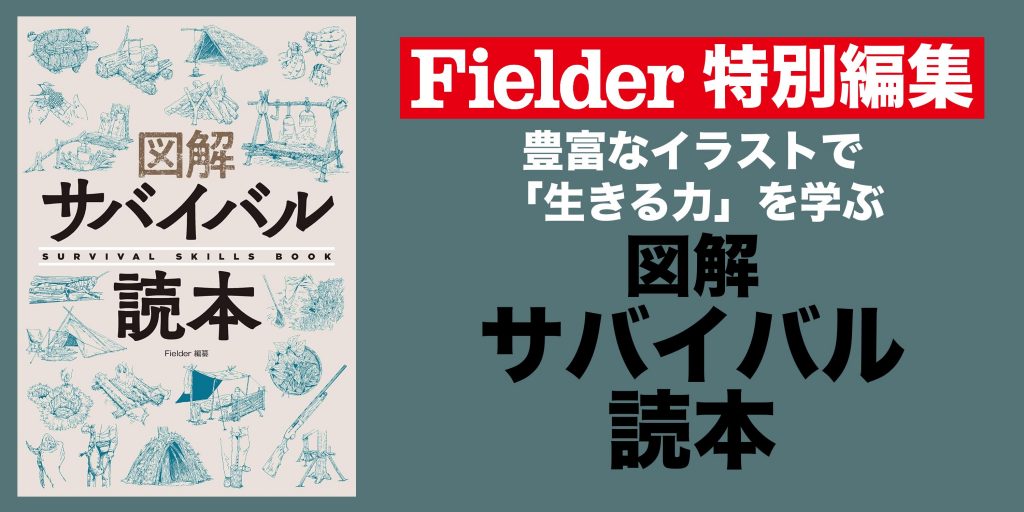氷期の足音はもう聞こえている?
気候変動というと、多くの人は地球温暖化や猛暑の脅威を思い浮かべるだろう。だがその一方で、我々が今いる「間氷期」──すなわち氷河時代の中の暖かい短い期間──が、実はすでに終わりに差しかかっている可能性があるという事実はあまり知られていない。
この地球の周期的な気候変動は、主に「ミランコビッチ・サイクル」と呼ばれる天文学的要因によって左右される。地球の公転軌道の形状や地軸の傾き、歳差運動などが数万年単位で変化し、それによって地球の受ける太陽エネルギー量が変動する。このサイクルに従えば、今の間氷期(ホロシーン)はすでに1万年を超えて続いており、歴史的なパターンから見ても、いつ氷期(氷河期)に入ってもおかしくない。地球の歴史を振り返れば、ここ100万年間は氷期が常態で、今のような温暖な気候こそ非常態なのだ。
実は人類が“氷河期”を食い止めている?
米国が誇るコロンビア大学のラモント・ドハティ地球観測所が、興味深い仮説を提唱している。2009年に発表された研究(Ganopolski et al., Nature 2009)によれば、現在の間氷期が長く続いている理由の一端は、人類の経済活動によって排出された二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスが、次の氷期の突入を先送りしているという可能性だ。
彼らのモデルでは、産業革命以前の大気中CO2濃度約240ppmが現代まで保持されていた場合、今世紀内にも氷期突入の引き金となり得たという。だが、ご承知の通り今のCO2濃度は420ppm(2025年時点)にも達しており、これによって氷期の開始は少なくとも数千年単位で先送りされた可能性が高いというのだ。
ちなみに、バージニア大学のウィリアム・ラジマン教授によると、大気中CO2濃度の増加はそもそも人間が農耕を始めたとされる7000年前からすでにはじまっているらしい。仮にこの増加がなければ、19世紀には氷期に入っていてもおかしくなかったのである。環境保全団体の視点から見ると”産業革命憎し”となるが、実際は”農耕憎し”と、人類の存在そのものを否定しなければならないだろう。
歴史が示す寒冷の代償
気温が下がることがどれほど致命的か──それはインカ帝国の事例が象徴的だ。15世紀末から16世紀にかけてのインカ帝国末期、わずか10年間のうち6年間が冷夏となった(Thompson et al., Science, 2000)。アンデスの高地で冷害が頻発し、作物の収穫が激減。これが食糧不足と社会不安を引き起こし、最終的に帝国はスペイン人の侵攻によって崩壊した。だが、スペインの武力以上に、飢餓がもたらした内部崩壊が本質的な原因だったとされる。
似たことは日本でも起きた。1993年、フィリピン・ピナトゥボ火山の大噴火による成層圏エアロゾルの影響で、東アジアでは日照が激減。日本では記録的な冷夏となり、コメの出来高は平年の約70%に落ち込んで「平成の米騒動」と呼ばれる混乱が起きた。政府は緊急措置としてタイなどから大量の米を輸入したが、その影響で世界中の米価格が急騰。日本という先進国ですら、1年の不作でパニックに陥る脆弱さを露呈した。
これが一時的な自然現象ではなく、「氷期の常態」として続いたとしたら?
”平成”に比べればまだマシだった直近の「令和の米騒動」ですら、主食である米の問題は国家レベルになる。高緯度に位置し、かつ自給率の低い日本にとっては、寒冷の常態化が人口激減と社会機能崩壊の現実的なシナリオとなるのだ。
氷期は数百年をかけてゆっくりやって来ない
それでも今を生きている人間にとって、気候変動は長大な現象で自分の人生には関係ないと思うだろう。実際、地球温暖化はその傾向が強いし、科学分野でも以前は“氷期と間氷期の切り替わりは数千年スパンの緩やかな変化”と考えられていた。だが、近年の氷床コアや堆積物の解析によって、それは誤りである可能性が浮上している。
グリーンランドの氷床コア研究(Dansgaard-Oeschger events)や、北大西洋の堆積物分析によれば、過去の気候変動にはわずか数年から十数年の間に平均気温が10℃近く下がった急激な変化が何度も起こっている。具体的には、3年程度で氷期の気候に突入した例も存在し、これは「ティッピング・ポイント(臨界点)」を超えることで気候が自己加速的に変化することを意味する。
数百年かけて進行する温暖化なら“科学技術の発展”というバッファが残されている。しかし、移行期間がたった3年となれば、準備など何もできずに日本がモスクワになるのを見届けるしかない。インカ帝国の人々には山を降りて低地で暮らすという逃げ道があったが、氷期への突入は全世界規模で逃げ道はないのだ。
自然回帰か、文明維持か
いま、我々は「温暖化対策」と称して、二酸化炭素の排出削減を進めている。確かに、極端な熱波や海面上昇、豪雨などへの対策としては不可欠であり、地球の長期的な安定を願うには正しい方向転換に見える。しかし、その一方で、もしこのCO2削減が地球の冷却化=氷期突入のブレーキを失わせるのだとしたら──?
これは二律背反の問いだ。CO2を出しすぎれば熱波で死に、出さなければ作物が実らず飢える。果たして、人類は「本来の自然」を尊重し、CO2を削減して氷期とともに生き延びる道を選ぶべきなのか。それとも、「本来の自然」の変動を温室効果によって制御し、あくまで文明を維持する選択をすべきなのか。まさに我々はその分岐点に立たされている。
※ここに書いた“大気中のCO2濃度増加が氷期突入を遅らせている”という研究がある一方、南〜北半球の間で莫大なエネルギー(熱伝達、炭素吸収etc)を循環させている超巨大海流「AMOC(大西洋子面循環)」が温暖化によって弱まる可能性を、コペンハーゲン大学のピーター・ディトレブセンらが指摘している。この流れが弱まれば南半球から北半球へ送られるエネルギーが少なくなるため、具体的には欧州付近で5〜10℃気温が低くなると予想されているのだ。まさにこれは上に書いた「ティッピング・ポイント」を超える氷期突入へのスイッチとなり得るものだろう。というわけで話をまとめると、究極的にはCO2を出しても出さなくても、そう遠くない未来に氷期で人口が激減することを覚えておこう!