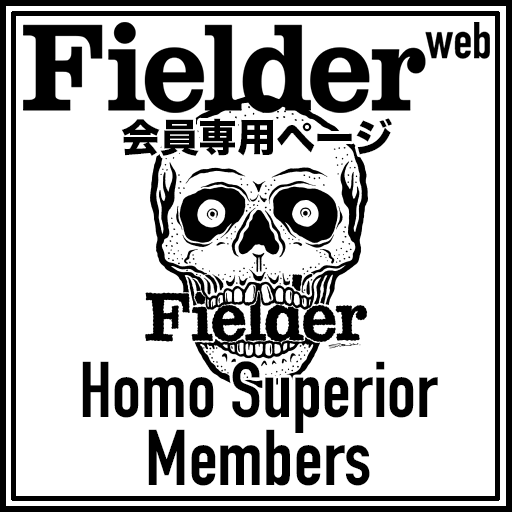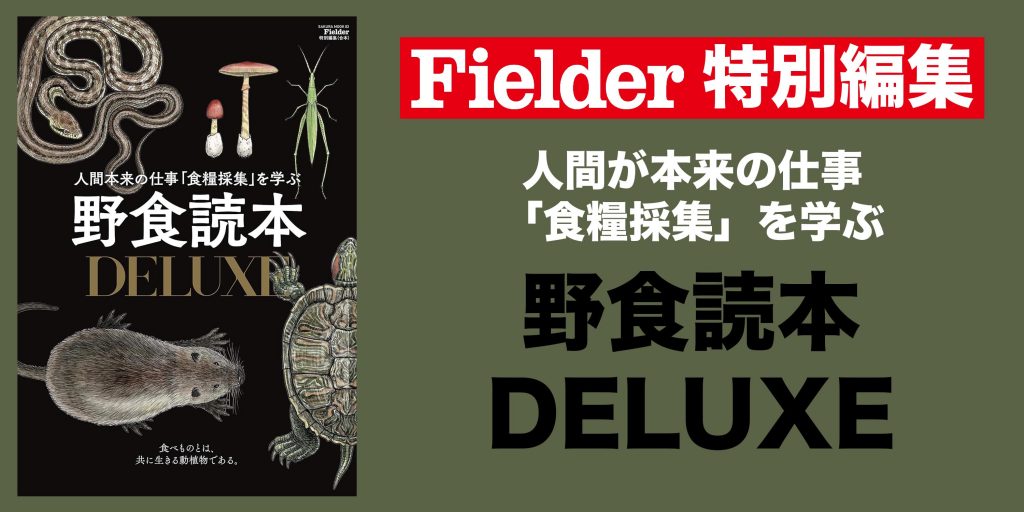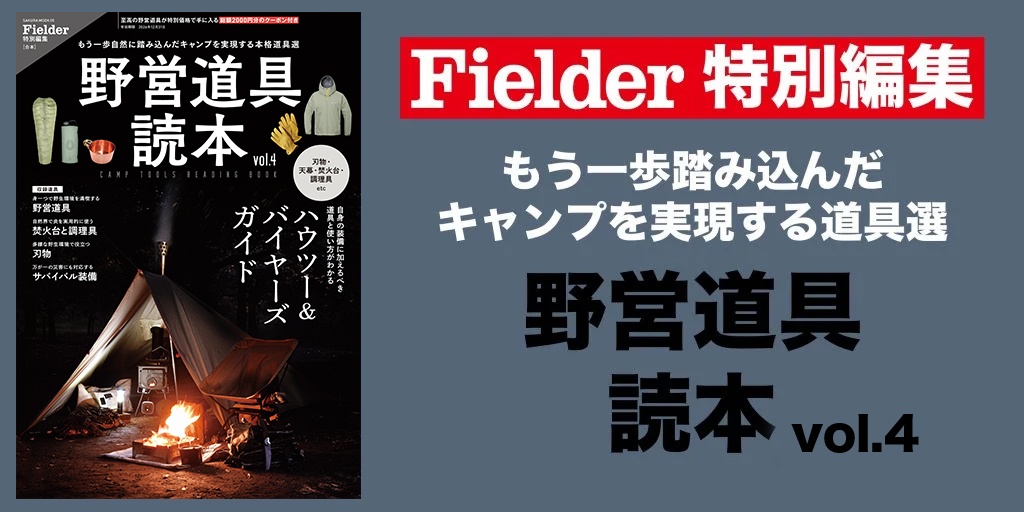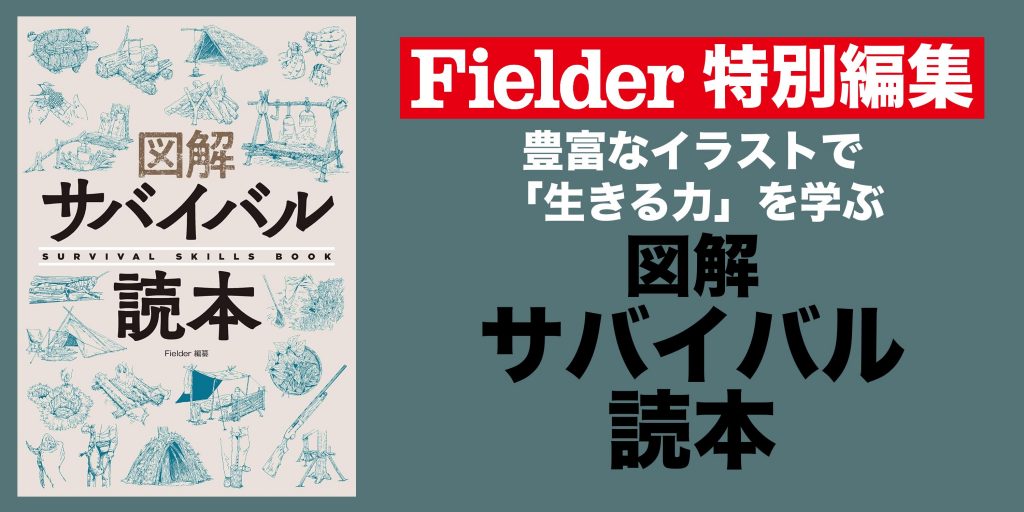ページ下にある見たい特集の写真やタイトルをクリックすると公開ページを閲覧できます
現場で考えて対応する〝サバイバルの基本〟を遊んで学ぶ
焚火総復習
炎を自在に使いこなして快適な野外生活を手に入れたい
人類がいつから火を使い始めたかは明確にわかっていない。
ただ、数十万年前の北京原人が日常的に火を使っていた痕跡はある。
今でこそ火はツマミ一つで自在にコントロールできる代物だが、
果たして我々ひとりひとりに、火を熾し、操る力は備わっているだろうか?
今号は寝床に並ぶ野営の醍醐味“焚火”をテーマに、
忘れ去られたホモ・サピエンス数十万年分のノウハウをさらっていく。
早速今季の野営にて、英知溢れる焚火を実践してもらえれば幸いである。
写真/降旗俊明
焚火をはじめる前に
まず大前提として、いくら燃料と名の付いたものでも、液体や固体のままでは燃えないことを意識したい。あくまで燃えているのは燃料から放出された可燃ガス(気体)なのだ。これを理解するには「ファイヤートライアングル」という図が有効である。
ファイヤートライアングルは火の発生に必要な要素を端的に表したモデルで、火災を理解し、消火方法を考える際によく用いられる。この図の通り、火の発生には燃料、酸素、熱の3要素が不可欠であり、それぞれが働き合い、連鎖的に化学反応が繰り返されることによって火は維持されるのだ。つまりは「熱」により「燃料」から可燃ガスが放出され、それが急激に「酸素」と結びついて燃焼する。この急激な酸化の際に発生した熱がまた、「燃料」から可燃ガスを引き出していくのである。普段から消火の際に行う「水を掛ける」「密閉する」「ガスの元栓を閉める」といった行為は、この3要素のどれかをファイヤートライアングルから引き抜き、連鎖反応を止めているのだ。
さて、この関係性を理解すると、誰でも火の成長過程を想像できるようになる。例えば焚火のはじまりがファイヤスターターで興した小さな火花だったとして、それに薪の可燃ガスを引き出すだけの熱量がないことは感覚的にわかる。火花の熱で可燃ガスを引き出せるのは綿毛などの火口であり、火口の熱で可燃ガスを引き出せるのは小枝などの焚き付け。最終的に焚き付けの熱をもってして、はじめて薪の可燃ガスを引き出せるのである。そして実は、焚火の成功率を高めるにあたって盲点となっているのもここにあるのだ。
「燃料となる薪には乾いたものを」「火床には空気が入るように」。これについては大半の人が経験的に知っていることだが、熱に対して意識している人は少ない。例えばティーピー型を完全に乾いた薪で組んでみても、なかなか焚き付けから薪へ火が移らない場合がある。もちろん、この組み方において空気の通り道は確保されているも同然。ここに問題があるとすれば、そもそも焚き付けの火が弱く、おまけにそれが外気にさらされていることから、薪から可燃ガスを引き出すだけの熱量に達していないのである。ティーピー型の利点は吸気効率の高さであり、外気を遮断して熱を蓄えることは本末転倒。この問題を解決するためには、大量の焚き付けを仕込んで盛大に熱を発生させれば良いのだ。
また、ほかにもこんな状況に出くわした方は多いだろう。薪には火が移ったものの、しばらく目を離している間に火が消えてしまうパターンだ。薪はキャンプ場で購入した良いもので、火床にも十分空気が入っているとなれば、これもやはり熱に問題がある。多くの場合は焚火を続けているうちに薪が炭化して小さくなり、最初に薪を組んだ時よりそれぞれの間隔が広がっているのではないだろうか。薪は完全な灰となるまで化学反応を繰り返す力があるため、こんな時は空気の通り道を考えつつ再度一箇所に集め直してやれば良い。互いの熱が作用し合い、再び消えにくく安定した火を上げるはずである。
※この記事は2018年8月発売『Fielder vol.41』に掲載されたものです。
SEA TO SUMMIT 2018 江田島(広島県)
これまでにも本誌でレポートしてきたモンベルの環境スポーツイベント「シートゥーサミット」。今回は瀬戸内海に浮かぶ広島の江田島が舞台。自然豊かなこの島を、海、里、山の3方向から満喫!
文/井上大助 写真/杉村 航 取材協力/江田島市、モンベル